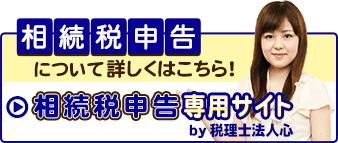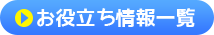相続税申告
相続税申告が必要な方や、相続税申告が必要か確認したいという方は、税理士法人心にご相談ください。
相続税申告は、各種特例等を適切に活用できるかどうかで、税額が大きく変わってくることも少なくありません。
相続税法や関連法令、各種通達等に精通している税理士が、相続税のお悩みをお伺いしたうえで、相続税申告をしっかりとサポートさせていただきます。
1 相続税専門の税理士が対応
税理士であれば,すべての税理金の専門家と思われがちですが,なかには企業の顧問業務がメインで主に所得税や法人税の申告・記帳代行を行っており,相続税申告は年に1~2件という税理士もいます。
相続税は,不動産の評価や非上場株式の評価など,高い専門性が求められる分野ですので,税理士法人心では,相続税専門の税理士が,相続税の申告業務を行わせていただきます。
2 税理士費用の『業界最低水準』を目指す
税理士法人心では,税理士費用を「安くする」ことにこだわっています。
税理士が相続税申告を集中的に取り組み,経験を積んだ税理士が申告書の作成を行うことで,高い品質を保ちながら無駄を省き,ハイスピードでローコストな申告書の作成を行うことを目指しています。
3 相続税申告額がわかる無料簡易診断サービスも実施
相続が発生した方すべてが,相続税の申告書の作成が必要になるわけではありません。
相続財産が「基礎控除額」を下回る場合,申告書作成の必要はありません。
また,申告書の作成は必要となりますが,小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例などの特例を利用して申告することで,相続税が0円になることもあります。
相続税の申告額がご不安な方は,まずは無料簡易診断サービスをご利用ください。
4 面倒な資料収集や手続きは税理士が代行
相続税申告と納税は,10か月以内という期限がありますので,それまでに必要な書類をすべて集めて申告書を作成しなければなりません。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本,作成した相続人関係図,遺言書や遺産分割協議書の写し,相続人全員の印鑑証明書だけではなく,様々な特例を活用する場合は,更に何十種類もの書類が必要となります。
お仕事をされているなど,平日の日中に動くことが難しい場合,集めるのにかなり時間や手間暇がかかります。
税理士法人心では,このような資料収集や手続きも税理士が代行しますので,お忙しい方でも安心です。
5 費用
相続税に関するご相談は,原則として無料で対応させていただきます。
最寄り駅から徒歩2分
当事務所は、名古屋駅から徒歩2分とアクセスの良い場所にあります。すぐ近くに駐車場もありますので、お車の方も徒歩の方もお気軽にお立ち寄りください。
相続税の申告の期限
1 原則10か月以内に申告しなければならない

相続税の申告については、原則、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
相続の開始があったことを知った日とは、基本的に、被相続人が死亡したことを知った日をいいます。
たとえば、令和6年7月1日に被相続人が亡くなったことを知った場合は、相続税の申告の期限は、令和7年5月1日となります。
また、10か月後が土日祝日の場合は、次の平日が相続税の申告の期限となります。
相続税の申告の期限の詳細については、以下の国税庁ホームページもご参照ください。
参考リンク:国税庁・相続税の申告と納税
2 10か月の期限に間に合わなかった場合のデメリット
万が一、10か月の期限に間に合わない場合、税務調査に突然入られたり、延滞税や無申告加算税、重加算税といった追徴課税がされたり、相続税を抑える小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減控除を使えなくなったりするといった、様々なデメリットを負う可能性があります。
特に、重加算税となった場合、無申告の場合だと、40%の税率が課せられることになります。
たとえば、本来1000万円の相続税を支払わないといけないにも関わらず、期限を過ぎてしまい、重加算税を課せられた場合、追加で400万円も大金を支払う必要があります。
さらに、これとは別に延滞税もかかってきます。
そのため、10か月の期限については、厳守していただき、できる限り期限内に申告を行った方が良いでしょう。
3 相続税の申告の期限に間に合わない場合の対処法
万が一、相続税の申告の期限に間に合わなかった場合は、気づいた時点で、できる限り早めに、期限後でも、相続税の申告を行った方が良いでしょう。
一番リスクが高いのは、税務調査に入られるまで、申告をせず、放置することです。
そのため、できる限り早めに、遺産の分割が相続人間で決まっていなかったとしても、相続税に詳しい税理士に相談し、申告を済ませておいた方が良いでしょう。
申告後、他に遺産が見つかった場合など、相続税の修正が必要な場合は、一度申告した後に、修正申告を行うこともできます。
相続税を適切に申告・納付しないとどうなるか
1 刑事罰になる場合がある

相続税を適切に申告しなかった場合、最悪のケースだと、懲役や罰金を科せられる場合があります。
実際、相続人が、相続財産から現金、預貯金等の一部を除外するなどして内容虚偽の相続税申告書を提出し、相続税合計1億7676万円を免れた事案で、裁判所は、当該相続人を懲役1年6月、罰金2500万円、懲役につき執行猶予3年に処しました(名古屋地判平成29年6月1日)。
2 重加算税が科せられる場合がある
また、懲役や罰金が科されなくても、悪質な場合は、重加算税が科せられる場合があります。
国税庁の重加算税の運用については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
※参考リンク:相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)/国税庁
重加算税の場合、申告をしていない場合は原則40%の税金が追徴され、過少に申告していた場合は、原則35%の税金が追徴されることになります。
たとえば、本来は1000万円の相続税を納めなければならない相続人が申告さえしていない場合、その相続人は、本来納めるべき1000万円に加え、重加算税として400万円を追加で納める必要があります。
また、本来は1000万円の相続税を納めなければならない相続人が500万円しか相続税を申告・納税していない場合、その相続人は、本来納めるべき500万円(1000万円-納付済みの500万円)に加え、175万円(500万円×35%)を納める必要があります。
3 過少申告税や無申告加算税が科せられる場合があ
さらに、重加算税が科せられない場合、たとえば、遺産の調査がしっかりできておらず、遺産の漏れがあった場合などでも、過少申告加算税や無申告加算税が科せられる場合があります。
国税庁の過少申告加算税や無申告加算税の運用については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
※参考リンク:相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)/国税庁
過少申告加算税では、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりませんが、税務調査を受けてから修正申告をした場合や更正を受けた場合は、最大15%の税金が追徴されます。
また、無申告加算税の場合、過少申告加算税とは異なり、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合でも、5%の税金が追徴され、税務調査を受けてから修正申告をした場合や更正を受けた場合は、税制改正により令和6年1月1日以降に申告期限が到来するものについては、最大30%の税金が追徴されることになりました。
なお、税制改正の概要については、財務省のホームページをご確認ください。
※参考リンク:税制改正の概要/財務省
4 延滞税がかかる
以上のような重加算税や過少申告加算税が科せられる場合、それに加えて延滞税が科せられます。
延滞税については、利子のようなもので、たとえ加算税が科せられない場合であっても、延滞税を支払わなければならない場合があります(延滞税の詳細については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
※参考リンク:延滞税について/国税庁
延滞税の税率については、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなります。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間であれば、2か月を経過するまでの日の期間は、2.4%、2か月を経過する日の翌日以降の期間は、8.7%となっています。
5 税理士に依頼しても適切に申告・納付できるとは限らない
このように、相続税を適切に申告・納付しない場合、最悪のケースでは刑事罰に処せられる可能性があり、刑事罰にならない場合でも、重加算税や、過少申告加算税や無申告加算税、延滞税を支払う必要があります。
また、税理士に依頼した場合であっても、その税理士が相続税に詳しいとは限らず、万が一、相続税に詳しくない税理士に依頼してしまった場合、相続税を適切に申告できず、重加算税や過少申告加算税等のペナルティを課せられてしまう場合あります。
そのため、相続税を適切に申告するためにも、相続税については、相続税に詳しい税理士にご依頼されることをおすすめします。
相続税申告への対策として事前にできること
1 ご生前に相続税のシミュレーションする
相続税は、誰が、どの遺産を相続するかによって金額が変わります。
そのため、あらかじめ相続税に詳しい専門家に相談した上で、まずは相続後の税金の金額をシミュレーションしておくのがよいかと思います。
2 相続税の申告期限に間に合わせるために対策しておくこと

⑴ 相続税の申告期限
亡くなったことを知った日の翌日から10か月が相続税の申告期限です。
⑵ 申告期限に間に合わないデメリット
遺産分割がまとまらない等の理由で申告期限に間に合わない場合でも、いったん相続人の間で法定相続分に応じて分けたと仮定した上で、「相続税を安くする特例を使わない」状態で相続税を計算し、納税する必要があります。
期限までに一度申告・納税の手続きを行い、さらに遺産分割がまとまった後に手続きを行うと、払いすぎた相続税を更正の請求によって返してもらうことができます。
しかし、いったんは特例が使えない状態で高い相続税を一括で相続人が納めなければならないという点では、このような事態に陥らないようにすることも、相続税申告・納付をスムーズに行うための対策といえます。
⑶ 期限に間に合わなくなる主な原因は遺産分割
相続税の申告期限までに行わなければならないものの中で最も時間がかかる作業は、遺産分割をまとめることです。
相続人同士の協議だけで終わるのであれば、早ければ1日、かかっても数か月で終わることもあります。
万が一協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停になると、半年~1年以上かかることもありますので、そうなると相続税の申告期限には間に合わない可能性も出てきます。
また、調停でも決着がつかない場合は、審判手続きになります。
審判になった場合には、3年以上の時間がかかることもありますので、相続税の申告期限には確実に間に合わなくなってしまいます。
⑷ 遺言があれば遺産分割は不要
適切な遺言書を作成しておけば、誰がどの遺産を相続するのかを決めるために遺産分割の協議を行う必要はありません。
最も時間がかかる遺産分割を行わずに済みますので、速やかに相続税の申告手続きに進むことができます。
また、申告期限に間に合わせるためにいったん仮で申告をする必要もなくなりますので、初めから相続税を安くする特例を使った状態で計算し、申告・納付をすることができ、納税の負担を減らせます。
すなわち、遺言書を作成することも相続税の申告期限に間に合わせるため・相続税の納付をスムーズに行うための対策であるといえます。
相続税申告の流れ
1 相続税の申告には期限がある

相続税の申告には、期限があります。
相続人らの申告の必要な方が、相続が開始したことを知った日から10か月です。
この期限までに、以下のように必要な書類を集めた上、提出書類を作成し、税務署に申告をしなければなりません。
2 相続人に関する資料を集める
相続税の申告にあたっては、相続人に関する資料を集める必要があります。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍が必要です。
相続人に関する資料が必要とされるのは、法定相続人の数によって相続税の基礎控除額が異なることや、遺産分割の当事者が誰なのかを確認する必要があることなどの理由があります。
3 相続財産に関する資料を集める
また、相続財産に関する資料を集める必要があります。
亡くなった方が、どのような財産を持っていたかが不明な場合には、その調査をすることも必要です。
相続財産に関する資料として、例えば不動産については、登記簿謄本(登記事項証明)、公図、固定資産評価証明書などが必要になります。
預貯金や金融資産については、亡くなった日の残高証明書などが必要です。
このように、亡くなった方のプラスの財産に関する資料の他に、マイナスの財産に関する資料も必要です。
例えば、亡くなった方に借入れがあればその借入れに関する資料、葬儀代や医療費を支払っていればこれに関する資料が必要になります。
4 相続財産を取得する内容を決める
相続人らが相続財産をどのように取得するのかを決める必要があります。
亡くなった方が遺言書を作成しており、その遺言書どおりに相続財産を取得するのであれば、その内容どおりで取得したということでよいでしょう。
ただ、相続人同士で遺言書の内容と異なる分け方をするために遺産分割協議をすることも可能です。
このような遺産分割協議をする場合や遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した上で、相続財産を取得する内容を決めるとよいでしょう。
5 申告書類の作成と納付
上記のとおりの準備をした上で、相続税の申告書類を作成する必要があります。
相続税の知識がないと、申告書類を適正に作成することは難しいと考えられますので、相続税に詳しい税理士に相談するか、申告書類の作成を依頼するのがおすすめです。
相続税の納付も、この期限までにする必要がありますのでご注意ください。