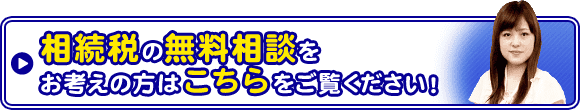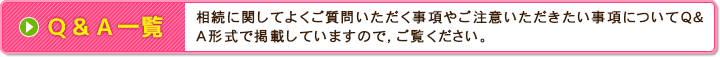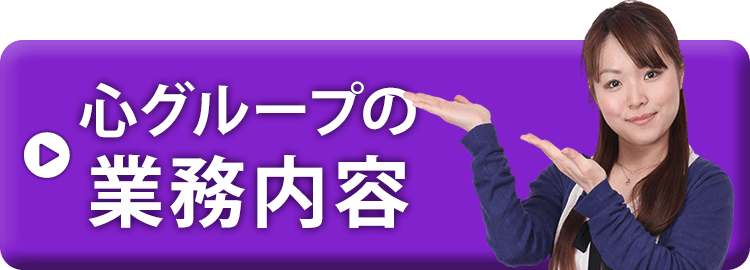生前贈与の手続きと流れは?必要書類や注意点などを解説
1 生前贈与とは?
生前贈与とは、ご自身がお亡くなりになる前に、保有している財産の一部または全部を他人(たとえば子や孫)に無償で譲り渡すことをいいます。
相続によって財産が移転する前、つまりご存命の状態で財産を移すことから、「生前」の「贈与」と呼ばれます。
原則として、暦年(1月1日~12月31日)で評価額が110万円を超える財産を受け取ると、受贈者(贈与を受けた方)に贈与税が課せられます。
ただし、贈与税には、税金を減額できる制度も設けられているため、一定の条件を満たす場合には税額を抑えることも可能です。
生前贈与は、相続税対策の手段としても活用されており、適切に行うことで将来の税負担を軽減できることもあります。
2 生前贈与のメリット
⑴ 自由度が高い
生前贈与は、ご自身の意思で、誰に、どの財産を、どのタイミングで与えるかを決定できます。
相続の場合、発生時期をご自身で決めることはできず、誰がどの財産を取得するかについても、法定相続分や相続人の話し合いで決まります。
生前贈与によって、まだ若年の子や孫を重点的に支援したい場合や、経営している会社の株式を事前に後継者候補の方に移転させたいという要望も実現可能です。
⑵ 資産の有効活用
子や孫の結婚・子育て資金、住宅取得資金、教育資金など、受贈者のライフステージに合わせたサポートをすることが可能です。
相続の場合、例えば90歳でお亡くなりになられると、相続人も60歳代であるということもあり、子が資金を必要とするタイミングで支援することができません。
生前贈与であれば、必要な時に支援を行えることで、贈与者・受贈者ともに満足度の高い財産移転を実現することができます。
⑶ 相続税対策
贈与により財産を相続開始前に移転することで、将来の相続財産を減らし、相続税を軽減できる可能性があります。
例えば、毎年基礎控除内(110万円以内)の贈与を継続することで、大きな資産移転を非課税で行うことができます。
ただし、定期贈与(決められた期間に一定額を受け渡すことが決められている贈与)とみなされないように注意する必要があるほか、相続開始前3年以内(2024年以降は段階的に7年以内)の贈与は相続税の対象になり得る点にも配慮が必要です。
3 生前贈与の流れ
⑴ 贈与の内容を検討する
前提として、誰にどの財産を贈与するかについて検討する必要があります。
贈与する財産(現金、預貯金、不動産、株式など)や、贈与する相手によって、手続きや税務上の取扱いが異なることがあるため、事前の検討がとても大切になります。
⑵ 贈与契約書を作成する
贈与は契約であり、法律上は口頭でも成立しますが、後のトラブルを防止することや、税務署への説明が求められた場合に備え、多くの場合贈与契約書を作成しておきます。
贈与契約書には、贈与者・受贈者の氏名や住所、贈与する財産の内容、贈与日(契約成立日)などを記載します。
⑶ 財産の移転
現金や預貯金であれば銀行振込、不動産であれば登記手続き、株式であれば名義変更など、受贈者に対する財産の移転を行います。
移転の方式や移転日(移転の期限)についても、贈与契約書に記載することが多いです。
⑷ (必要な場合)贈与税の申告と納付
暦年課税であれば、1月1日から12月31日までの贈与額が110万円を超えた場合、受贈者が贈与税の申告と納付をする必要があります。
4 生前贈与を行う上での注意点
⑴ 贈与契約の成立を明確にする
贈与税は、文字どおり贈与に対して課される税です。
財産の取得が贈与によるものでないとみなされると、そもそも実質的には財産が移転していないとされる可能性や、別の税(所得税など)が課せられてしまう可能性があります。
贈与は契約行為であるため、贈与者と受贈者双方の合意が必要です。
そして、当事者双方の意思表示は客観的に示せるようにすることが大切ですので、贈与契約書などを作成しておきます。
⑵ 相続開始前の贈与は相続財産に加算されることがある
贈与者が死亡する前3年以内(2024年以降は段階的に7年以内)の贈与は、原則として相続財産に加算されます。
節税目的で行ったとしても、相続税の課税対象に含まれることがある点には注意が必要です。
⑶ 名義預金とみなされないようにする
⑴と関連しますが、形式的に財産の名義が移転していても、実態として贈与がなされていない場合、その財産は贈与者に属したままになります。
典型的なものとして、名義預金が挙げられます。
形式的な贈与者が子や孫の名義の預金口座に入金し、その口座を管理し続けている場合、贈与として認められないことがあります。
名義預金とみなされた場合、その預金は相続開始時に相続財産に含まれることになり、相続税額が上がることになります。
金銭を受贈者名義の預金口座に入れて贈与する場合、受贈者がその口座を管理・使用できる状態にしておくことが大切です。
⑷ 贈与税以外の税にも注意
不動産の贈与を行うと、贈与税だけでなく、登記手続き時の登録免許税や不動産取得税も発生します。
贈与税以外の税も含めた、トータルの税負担を予め検討しておくことも大切です。
弔慰金が相続税の対象になる場合 贈与税の税率と税額の計算方法について