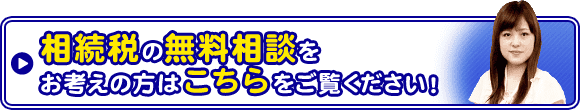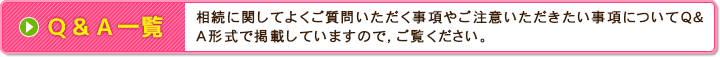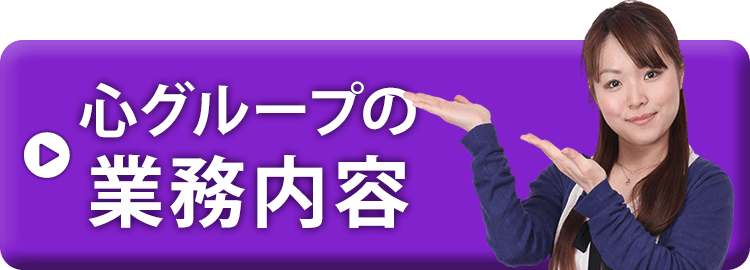相続税対策(節税のために出来ること・準備しておくこと)
1 相続税対策とは?
相続税対策とは、将来の相続発生に備えて、予め相続税の負担軽減を可能にするための事前準備をすることを指します。
相続税は、相続財産(みなし相続財産含む)の評価額に対して課税されます。
超過累進課税方式によって課税されますが、その税率は最大で55%と高額になることもあります。
十分な対策を行わずに相続が発生すると、相続税の負担が重くなり、場合によっては相続人が納税資金を確保するにも苦労することがあります。
相続税対策には、生前贈与を活用する、相続財産の評価額を下げる、基礎控除や各種非課税枠を活用するなどの方法が挙げられます。
ただし、対策の方法によっては贈与税など他の税金が課せられる可能性もありますので、制度の内容を正しく理解して進めることが重要です。
2 生前贈与を活用した相続税対策
⑴ 生前贈与と相続税
生前贈与は、相続発生前に財産を贈与し、将来の相続財産を減らすことで相続税の負担を軽減する方法です。
⑵ 暦年贈与の非課税枠の活用
原則として、暦年(1月1日~12月31日)で評価額が110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
長期的にコツコツと贈与を行うことで、大きな節税効果を得られる可能性があります。
ただし、定期贈与(決められた期間に一定額を受け渡すことが決められている贈与)とみなされると贈与税が課せられる可能性があります。
また、相続開始前3年以内(2024年以降は段階的に7年以内)の贈与は、相続税の対象になり得る点にも配慮が必要です。
⑶ 教育資金贈与の非課税制度
直系尊属(祖父母や父母など)から教育資金を一括贈与する場合、一定の要件を満たせば最大1500万円まで非課税となります。
この制度の利用条件はとても複雑であり、時折変更されることもあるので、利用の際には最新情報を確認しましょう。
⑷ 結婚・子育て資金贈与の非課税制度
直系尊属(祖父母や父母など)から結婚・子育て資金を一括贈与する場合、一定の要件を満たせば最大1000万円まで非課税となります。
この制度の利用条件はとても複雑であり、時折変更されることもあるので、利用の際には最新情報を確認しましょう。
⑸ 相続時精算課税制度の活用
この制度を選択した場合、年間110万円までの基礎控除内の贈与と、合計2500万円までの贈与については贈与税がかかりません。
将来の相続時に、贈与分を合算して相続税を計算します。
年間110万円の基礎控除枠と、合計2500万円の枠を超えた分については、一律20%の税率で課税されます。
60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から、18歳以上の子や孫が贈与を受ける場合に選択できる制度です。
相続時精算課税制度を一度選択すると、その後の贈与については相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻ることができないという点には注意しましょう。
3 財産の組み替えによる相続税対策
相続税は、相続財産の「評価額」に対して課せられる税です。
相続税算定における財産評価方法の性質上、財産の種類によって課税額が変わります。
現金や預貯金は額面どおりの評価額になりますが、不動産は路線価や固定資産税評価額など、時価(市場価格)よりも低く評価される場合があります。
この差に着目し、財産の組み替えによって、相続税算定時の相続財産の評価額を下げられることがあります。
例えば、現金や預貯金を利用して賃貸用不動産を購入すれば、土地や建物の評価額は時価より低くなり、さらに賃貸物件であれば借家権割合や借家権割合の控除ができます。
その結果、課税価格が抑えられ、相続税額を軽減する効果が期待できます。
ただし、不動産の購入には、管理維持費、価値変動リスクなども伴うため、税金面だけでなく総合的な判断が必要です。
また、生命保険の活用も有効です。
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、現金や預貯金をそのまま持っているよりも税額を抑えられます。
さらに、生命保険金は遺産分割協議を経ることなく受け取れるため、相続人の納税資金の確保にも役立ちます。
4 特例や制度を利用した相続対策
⑴ 相続税負担を軽減する特例や制度の存在
相続税は最大税率が55%という負担の大きな税ではありますが、政策上の配慮等によって、一定の条件を満たすことで課税額を大幅に軽減できる特例や制度が用意されています。
以下、代表的なものについて説明します。
⑵ 小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅の敷地や、事業のために使用していた土地について、最大80%まで評価額を減額できる制度です。
例えば、居住用宅地であれば、一定の条件を満たすことで330㎡までは評価額を80%下げることが可能であり、大きな節税効果が期待できます。
⑶ 配偶者の税額控除
配偶者が相続する財産に対しては、1億6000万円または法定相続分までは相続税が課せられません。
5 相続税対策のお悩みは早めに専門家にご相談ください
相続税対策は、短期間で完結するものではなく、年単位での計画が必要になることもあります。
例えば、暦年贈与を活用する場合、少額を長期的に贈与することで効果が出始めることから、早めに着手する必要があります。
また、税に関する制度は比較的頻繁に改正されるため、現在有効である制度が、数年後も同じ条件で利用できるとは限りません。
家族構成や財産状況の変化によっても、最適な対策方法は変わります。
そのため、相続税対策は相続に強い税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた検討をすることが大切です。
相続税は多額の資産を有している場合に課せられる税というイメージがありますが、都市部に自宅を有している場合などにおいては、相続税が課せられることも多いです。
相続はいつ発生するかわからないことから、健康状態が良好であるうちから相続税対策を進めていくことが大切です。
贈与税の税率と税額の計算方法について 孫に生前贈与する?孫への生前贈与のやり方や注意点を解説