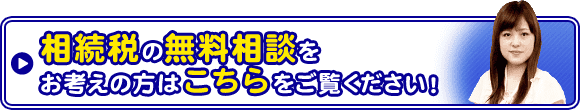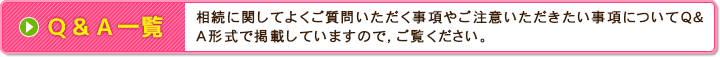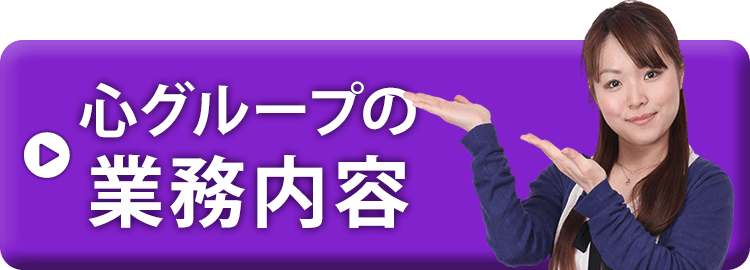贈与税の税率と税額の計算方法について
1 贈与税とは?いくらから贈与税がかかる?
贈与税とは、生前に財産を他人(親族を含む)に無償で譲り渡した場合に、譲り受けた側に課される税金です。
例えば、親から子へお金や不動産、株式などを譲り渡した場合、それが贈与とみなされ、一定額を超えると贈与税の対象になります。
贈与税がかかるのは、原則として暦年(1月1日~12月31日)で合計110万円(正確には評価額が110万円)を超える贈与を受けた場合です(相続時精算課税を選択した場合は異なります)。
逆にいえば、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
この110万円という金額を、基礎控除額といいます。
例えば、1年間で親から80万円、祖父母から50万円の贈与を受けたとすると合計130万円となり、110万円を超えるため贈与税の申告、納付が必要になります。
2 贈与税の2つの税率
⑴ 暦年課税の場合
暦年課税は原則的な方式であり、毎年1月1日から12月31日までに受け取った贈与の合計額から110万円の基礎控除をした後の課税対象額に応じた税率が適用されます。
税率は10%から55%までの超過累進課税で、金額が多いほど高くなります。
さらに、贈与者と受贈者の関係によって、累進課税が適用される金額が変わります。
⑵ 相続時精算課税制度を選択した場合
60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から、18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に選択できる制度です。
この制度では、年間110万円までの基礎控除内の贈与と、合計2500万円までの贈与については贈与税がかからず、将来の相続時に合算して相続税を計算します。
年間110万円の基礎控除枠と、合計2500万円の枠を超えた分については、一律20%の税率で課税されます。
この制度を一度選択すると、その後の贈与については相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻ることができない点に注意が必要です。
3 贈与税の計算方法(暦年課税)
⑴ 課税価格の算定
まず、贈与を受けた金額から、基礎控除額110万円を差し引き、課税価格を算定します。
例えば、700万円万円の贈与を受けた場合、課税価格は590万円(700万-110万円=590万円)になります。
⑵ 税率の適用
次に、課税価格に対して税率を掛けあわせることで、贈与税額を算定します。
算定の際には、国税庁が公開している速算表を用いると便利です。
参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)
例として、直系尊属から700万円の贈与があった場合(特例税率)の贈与税額は次のようになります。
590万円 × 20% = 118万円
118万円-控除額30万円 = 贈与税額88万円
4 贈与税が非課税・減税になるケース
⑴ 非課税または減税になる制度があります
贈与税は比較的高額になりやすく、負担が大きくなることもありますが、政策上の目的などにより、一定の条件を満たす場合には非課税または減税される制度が設けられています。
以下、代表的なものについて説明します。
⑵ 扶養義務者間で授受される生活費や教育費
親から子など、扶養義務者から通常必要とされる生活費や養育費を渡す場合、必要な都度直接与えているものであれば、贈与税の対象外とされます。
生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預貯金、株式や不動産などの購入資金に使用している場合には、贈与税の対象になり得ます。
⑶ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与
一定の条件のもとで、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得資金を受け取る場合には、最大1000万円(省エネ等住宅の場合)、まで非課税となる制度があります。
住宅の契約期限や年収制限など条件があり、制度の内容も変わることがあるため、利用する際には最新の情報を確認する必要があります。
⑷ 直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
一定の条件のもと、直系尊属から結婚・子育て資金に充てるための金融機関等との資金管理契約に基づいて信託受益権を取得した場合、その信託受益権または金銭等の価額のうち1000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税を非課税にできることがあります。
この制度の適用を受けるにあたっての条件は複雑であり、制度内容の変更が起こることもあるため、利用を検討する際には最新の情報を確認する必要があります。
⑸ 直系尊属からの教育資金の一括贈与
一定の条件のもと、直系尊属から教育資金に充てるための金融機関等との資金管理契約に基づいて信託受益権を取得した場合、その信託受益権または金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税を非課税にできることがあります。
この制度の適用を受けるにあたっての条件は複雑であり、制度内容の変更が起こることもあるため、利用を検討する際には最新の情報を確認する必要があります。
生前贈与の手続きと流れは?必要書類や注意点などを解説 相続税対策(節税のために出来ること・準備しておくこと)