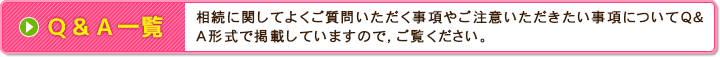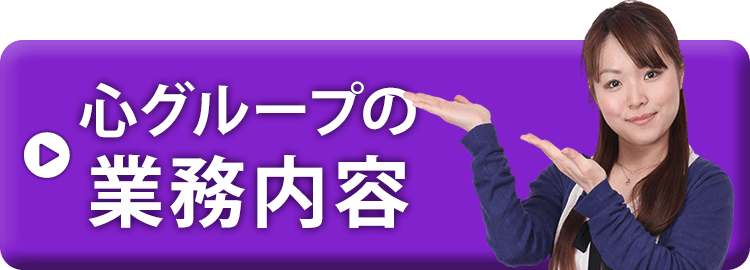死亡した人の口座をそのまま使うことの問題点
1 相続人間で訴訟に発展する可能性がある
基本的に、死亡した人の口座については、そのまま使うことによって、相続人間で訴訟に発展する可能性があります。
そもそも、死亡した人の口座について、銀行が当該口座の名義人の死亡を知らない限り、凍結されることは基本的にありません。
そのため、死亡した後も、ATMで口座からお金を引き出すことは可能です。
もっとも、死亡した後に引き出されたお金について、相続人全員の同意がない場合、相続人から、引き出したお金の返還請求をされることがあり、場合によっては訴訟に発展する場合もあります。
実際、死亡した後に、葬儀費用として数十万円を引き出し、その後の生活費としてもいくらか引き出した事案で裁判になり、結果として、引き出したお金の一部を返還しなければならなくなった事例もあります。
なお、死亡した後にお金を引き出した場合、民事事件だけでなく、刑事事件にも発展する可能性もありますので、注意が必要です。
2 相続放棄ができなくなる可能性がある
相続放棄を行う場合、死亡した人の口座をそのまま利用している場合、遺産を相続したものとして、相続放棄ができなくなる場合や一度認められた相続放棄が無効になる場合があります。
たとえば、死亡した人の口座で光熱費の支払いを行っていた場合、死亡した後もそのままにしておくと、実質的に、死亡した人の預金を使って光熱費を支払っていたということになり、遺産を相続したものとして、相続放棄ができなくなる可能性があります。
そのため、相続放棄を検討されている方は、なるべく早めに死亡した人の口座を凍結させ、光熱費等の支払いがある場合は、電力会社等にも、死亡の事実を伝えた方がよいでしょう。
3 口座が凍結した場合でもお金を引き出す方法
このように、死亡した後は、基本的に口座をそのまま利用しておくことは、トラブルに発展する可能性があり、おすすめしません。
もっとも、今後の生活費や相続税の支払い等で、どうしてもお金を引き出さなければならない場合もあるかと思います。
そういった場合、①一つの金融機関あたり最大150万円を引き出すことができる仮払い制度や、②家庭裁判所の判断により、150万円を超える金額でも引き出しが認められる可能性のある制度の2つの制度があります。
参考リンク:政府広報オンライン・知っておきたい相続の基本
どちらを使うのかについては、引き出す必要のある金額によっても異なりますので、詳細は専門家にご相談されることをおすすめします。
兄弟姉妹が亡くなった時に相続人になれる?相続割合や注意点 相続財産調査とは?自分でやる場合の注意点と専門家の選び方