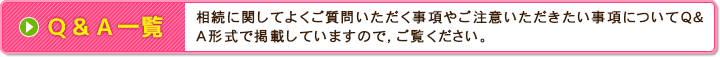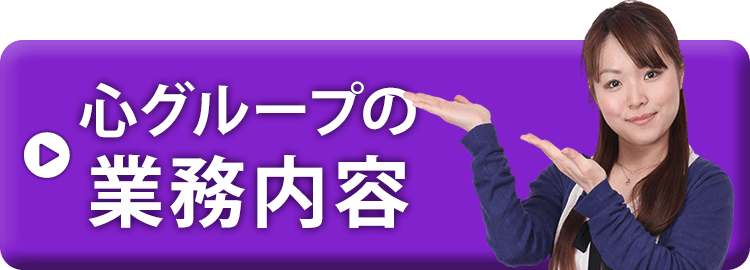兄弟姉妹が亡くなった時に相続人になれる?相続割合や注意点
1 兄弟姉妹の法定相続人の順位は?
相続の順位は法律で定められており、兄弟姉妹の順位は最も低く、3番目の順位となります。
具体的には、第1順位が子、第2順位が直系尊属(親など)、第3順位が兄弟姉妹になります。
なお、配偶者は常に相続人になります(ケースによって法定相続割合は変わります)。
2 兄弟姉妹が相続人になれる3つのケース
⑴ 配偶者がいて先順位相続人(子と直系尊属)がいない場合
配偶者のいる被相続人(亡くなられた方)にもともと子がいない場合や、子が先に亡くなられていた場合で、かつ両親や祖父母などの直系尊属が先に亡くなられていた場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
なお、子が先にお亡くなりになられていても、その子に子(被相続人からみた孫)がいる場合には、代襲相続が発生するため兄弟姉妹は相続人になりません。
⑵ 配偶者がおらず先順位相続人(子と直系尊属)もいないケース
被相続人に配偶者がいない場合であっても、先順位相続人がいなければ、兄弟姉妹は相続人になります。
⑴とは、兄弟姉妹の法定相続割合が異なります。
⑶ 遺言書で兄弟姉妹に相続させる旨の記載があるケース
子や直系尊属がいる場合であっても、兄弟姉妹に財産を相続させる旨が記載された遺言書がある場合、兄弟姉妹も相続財産を取得できます。
配偶者、子、直系尊属には遺留分が存在しますので、遺言書によって兄弟姉妹に財産を相続させる際には、遺留分を侵害しないように留意する必要があります。
3 3つのケースごとの遺産相続の割合
⑴ 配偶者がいて先順位相続人(子と直系尊属)がいないケース
法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、さらにその人数で案分します。
仮に兄弟姉妹が3人いた場合、1人あたりの相続割合は12分の1になります。
⑵ 配偶者がおらず先順位相続人(子と直系尊属)もいないケース
この場合は、兄弟姉妹がすべて相続することになります。
各兄弟姉妹の相続分は、人数で案分した割合になります。
例えば兄弟姉妹が2人である場合、それぞれ2分の1になります。
⑶ 遺言書で兄弟姉妹に相続させる旨の記載があるケース
遺言書を用いると、兄弟姉妹の相続割合は自由に決めることができます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。
遺留分は、相続人の構成によって変わります。
相続人が直系尊属のみである場合の遺留分は合計で3分の1、それ以外の場合には2分の1です。
4 兄弟姉妹が相続する際の注意点
⑴ 代襲相続が発生している場合
本来相続人になる方が、被相続人よりも先に亡くなられている場合、その本来の相続人の直系卑属(子など)が相続人になります。
この仕組みを代襲相続といいます。
兄弟姉妹相続において代襲相続が発生している場合、2つの注意点があります。
ひとつは、相続人の人数が多くなり、遺産分割が複雑化しやすくなる傾向にあるということです。
例えば、高齢の被相続人がお亡くなりになられた場合、兄弟姉妹もご高齢で、先にお亡くなりになられているということも多いです。
兄弟姉妹の方に子(甥や姪)がいた場合、代襲相続が発生します。
例えば、2人の兄弟姉妹が先に亡くなられていて、それぞれに子が3人ずついた場合、代襲相続人は6人になりますので、この6人で遺産分割協議を行う必要があります。
もうひとつは、再代襲はできないという点です。
子に対する相続が発生するケースにおいて、子と孫も先に亡くなっていたという場合、代襲相続が2代に渡って発生し、孫の子(ひ孫)が相続人になります。
これに対して、兄弟姉妹に相続が発生するケースにおいては、兄弟姉妹およびその子(甥や姪)が先に亡くなっていた場合、甥、姪の子に対する代襲相続は発生しません。
⑵ 配偶者にすべての財産を相続させる遺言がある場合
兄弟姉妹には、遺留分が存在しません。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、原則としては配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で財産を相続します。
そして、配偶者にすべての財産を相続させる旨が記載された遺言書がある場合には、配偶者がすべての財産を取得することになり、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
⑶ 相続税額が加算される
相続人が支払う相続税の金額は、被相続人との関係によって変わります。
被相続人の配偶者と一親等の血族(代襲相続人となった孫含む)以外の方が相続人になった場合には、相続税額は2割加算されることになっています。
5 遺産相続のお悩みは早めに専門家にご相談ください
遺産相続に関しては、検討や実施をしなければならないことが多岐に渡ります。
特に、兄弟姉妹相続が発生するケースは、相続関係が複雑になりがちです。
ご生前の段階においては、遺言の作成を検討することも多いです。
相続開始後は、代表的なものだけでも、相続人の調査、相続財産の調査、(遺言がない場合)遺産分割協議、預貯金や不動産の相続手続き、相続税の申告などを行う必要があります。
これらのなかには、期限が設けられているものもあります。
ご生前、相続開始後いずれの場合においても、相続に関するお悩みが少しでもありましたら、できるだけ早く相続の専門家に相談しましょう。
内縁の妻(夫)に相続させるための方法 死亡した人の口座をそのまま使うことの問題点