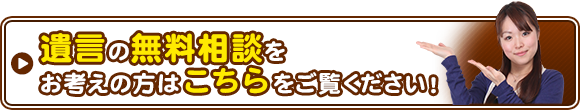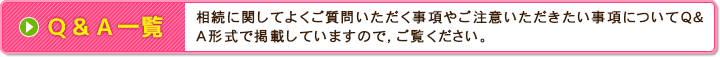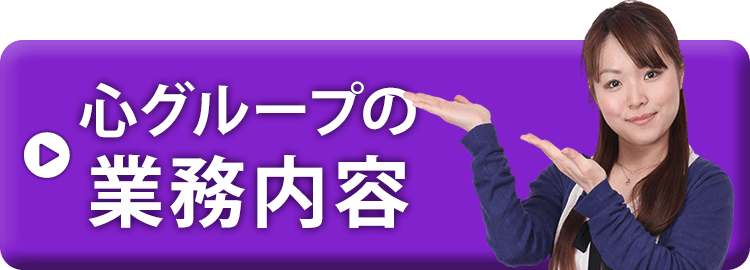遺言を作成する際にかかる費用
1 自筆証書遺言(手書きの遺言)の場合
手書きで作成する遺言(自筆証書遺言といいます)の場合、紙とペンとハンコさえあれば作成することができます。
そのため、自筆証書遺言の場合、費用はほとんどかかりません。
もっとも、自筆証書遺言は、条件を満たさないと無効になってしまう場合があるため注意が必要です。
たとえば、遺言に押印がされていない場合、それだけで基本的に自筆証書遺言としては無効となります。
また、遺産目録以外は全文自筆で書かなければいけないため、遺言の一部をパソコン等で印字した場合、自筆証書遺言としては無効となります。
なお、遺産目録をパソコン等で印字した場合、各ページに署名押印が必要です。
このように、自筆証書遺言はほとんど費用がかからず簡単に作成できますが、遺言が無効になる可能性があるリスクがあります。
また、作成した自筆証書遺言の保管場所が分からなくなってしまったり、紛失してしまったりするリスクもありますので、注意が必要です。
なお、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度を利用すれば、紛失してしまうリスクはなくなりますが、保管料3900円の他、住民票も添付する必要があるため、住民票の取得費用がかかります。
他方、法務局での保管制度を利用しない場合、保管料などはかかりませんが、遺言を作成された方が亡くなった後に、遺言の検認という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
参考リンク:裁判所・遺言書の検認
申立てに費用がかかりますし、この手続きを専門家に依頼した場合は10万円~20万円程度かかることがあります。
2 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)の場合
公証役場で作成する遺言(公正証書遺言)は、必要書類を公証役場に提出し、証人2人とともに、公証人の面前で遺言に署名、押印することで作成することができます。
公正証書遺言の作成のために必要となる書類として、たとえば、戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票、登記事項全部証明書、預貯金や株式の残高証明書等が挙げられます。
公正証書遺言の場合、まず、これらの必要書類の取得費用がかかります。
さらに、公証役場に支払う手数料と証人2名を公証役場に用意してもらう場合は、証人2人分の日当(1人につき、5000円~1万円前後)が必要となります。
公証役場に支払う手数料については、財産の総額や遺言書のページ数等によっても変わってきます。
なお、公正証書遺言の場合、公証人が遺言書の案文を作成してくれることもありますが、公証人によっては、テンプレート通りのものしか提案してくれない場合もあり、後々、遺言の内容をめぐって相続人間でトラブルになることもありますので注意が必要です。
3 専門家に遺言の作成を依頼する場合
遺言の作成を専門家に依頼する場合、専門家が遺言書の案文を作成し、基本的に、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する流れとなります。
そのため、専門家に遺言の作成を依頼した場合、これまで見てきた自筆証書遺言や公正証書遺言の作成費用に加えて、専門家への報酬が必要となります。
他方、専門家に遺言の作成を依頼する最大のメリットとしては、依頼した専門家が相続に詳しい場合、遺言を作成される方のご家庭の状況や相続税対策、後々のトラブルの予防、相続人の今後の生活等を考慮した、その方に適した遺言を作成してもらえることです。
遺言の内容次第で、相続税の金額が異なることがあり、また、将来相続人同士が揉める原因となってしまう可能性もあります。
そのため、遺言の作成については、相続に強い専門家にご依頼されることをおすすめします。
もっとも、専門家の中には、たとえば信託銀行などの金融機関の場合、遺言作成報酬が100万円を超えるところもありますので、実際にご相談される際は、事前に見積りを取っておいた方が良いでしょう。
なお、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、弁護士報酬として15万円~20万円のところが多く、金融機関に比べて5分の1の金額で遺言を作成してもらえるところが多いです。
私たちは、遺言について原則無料で相談をお受けしていますし、すでに遺言を作成されている方の場合、その遺言の内容を無料で診断させていただくサービスも実施していますので、お気軽にお問い合わせください。