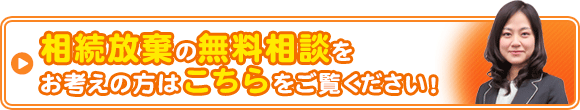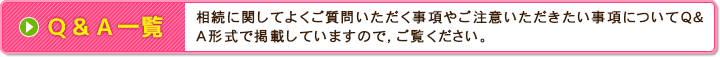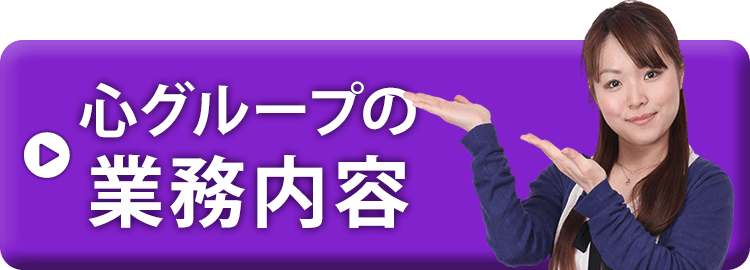相続放棄の必要書類を続柄別(子・兄弟姉妹・孫など)に紹介
1 相続放棄の必要書類は?
相続放棄を行う際には、相続放棄申述書に、相続関係を示すための戸籍謄本などの書類を添付して管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
一般的には、次の書類や資料が必要となります。
① 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
② 被相続人の戸籍謄本(被相続人との関係により必要な範囲は異なる)
③ 申述人(相続放棄をする相続人)の戸籍謄本
④ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
⑤ 収入印紙
このほか、相続の開始(被相続人の死亡)から3か月以上が経過してからの相続放棄申述をする場合には、相続の開始を知るのが遅くなった事情を説明するための資料を提出することもあります。
①、③~⑤については、被相続人との続柄に関係なく共通して必要になります。
②については、被相続人との続柄によって、収集しなければならない範囲が大きく異なりますので、以下詳しく説明します。
2 続柄別の相続放棄に必要な書類
⑴ 被相続人の子や代襲相続人が相続放棄をする場合
被相続人の子が相続放棄をする場合には、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と、相続放棄する子の戸籍謄本が必要になります。
子が先に亡くなっていて、子の子(孫)がいる場合、代襲相続によって孫が相続人になります。
この場合には、被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
⑵ 被相続人の直系尊属(親や祖父母)が相続放棄をする場合
被相続人に子がいないが直系尊属がご存命の場合や、子(代襲相続人含む)が全員相続放棄をした場合、直系尊属である親や祖父母などが相続人になります。
この場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続放棄をする直系尊属の戸籍謄本、既に亡くなっている直系尊属の戸籍謄本が必要になります。
親が先に亡くなっていて、祖父母がご存命の場合には、さらに親の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
被相続人の子が先に亡くなっている場合、子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
被相続人の直系卑属(子など)が全員相続放棄をしている場合には、そのことがわかる書類(相続放棄申述受理通知書の写しなど)が必要になります。
⑶ 兄弟姉妹や代襲相続人が相続放棄をする場合
被相続人に子や直系尊属がいない場合や、これらの方々が全員相続放棄している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続放棄をする兄弟姉妹の戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となります。
被相続人の子が先に亡くなっている場合、子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子(甥や姪)がいる場合、甥、姪が相続人になります。
この場合には、被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
先順位相続人(子や親など)が全員相続放棄をしている場合、そのことがわかる書類(相続放棄申述受理通知書の写しなど)が必要になります。
3 相続放棄の書類の入手方法や提出方法について
⑴ 戸籍謄本や住民票などの入手方法
相続人、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本は広域交付制度を用いることで、市役所等で取得することができます。
被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地にある市役所等で取得できます。
被相続人の住民票除票は、被相続人の最後の住所地のある市役所等で取得できます。
請求先の市役所等が遠方にある場合には、郵送による請求も可能です。
⑵ 申述書の書き方と提出先
相続放棄申述書のフォーマットは、家庭裁判所のホームページや窓口で入手できます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
申述書のフォーマットには、被相続人や申述人(相続放棄をする相続人)の氏名や本籍地など、身分に関することを記載するとともに、相続放棄するに至った事情や、被相続人の財産の概要などを記入します。
なお、相続放棄は理由や被相続人の財産状況にかかわらず可能ですが、これらの情報は後日裁判所が申述人に意思確認等を行う際に用いられることがあります。
複雑な事情がある場合には、申述書のフォーマットを使用せずに、ゼロから相続放棄申述書を作成することもあります。
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
直接持参をするか、郵送で提出します。
4 相続放棄は3か月の期限に注意
相続放棄には、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内という、とても短い期限が設けられています。
この期間は、熟慮期間と呼ばれることがあります。
熟慮期間内に相続放棄をするか否かを決定するとともに、相続放棄をする場合には管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出する必要があります。
相続放棄をせずに熟慮期間が経過すると、基本的には単純承認とみなされ、以降相続放棄をすることはできなくなります。
5 相続放棄をお考えなら早めにご相談ください
先述のとおり、相続放棄にはとても短い期限が設けられています。
相続放棄に必要な書類を揃えるのにも、一定の時間を要します。
そのため、少しでも相続放棄をお考えでしたら、できるだけ早くにご相談ください。
相続放棄は、基本的には1回しか行うことができない手続きです。
書類等に不備があり、相続放棄が認められなかった場合、再度申述をするのは困難です。
そのため、相続放棄に強い弁護士に手続きを依頼した方が、安全であるといえます。
また、申述が受理されると、基本的に撤回をすることはできません。
本当は相続した方が得だったということが後から判明しても、相続財産を取得すること等はできません。
相続放棄をするべきケースであるか否かという観点も含めて弁護士に相談することも大切です。
相続放棄の費用は?費用相場や弁護士・司法書士への依頼費用 相続放棄の期間は3ヶ月?期限を過ぎてしまった場合の対処法