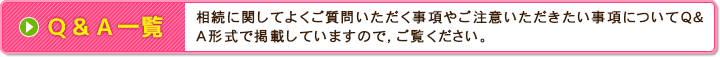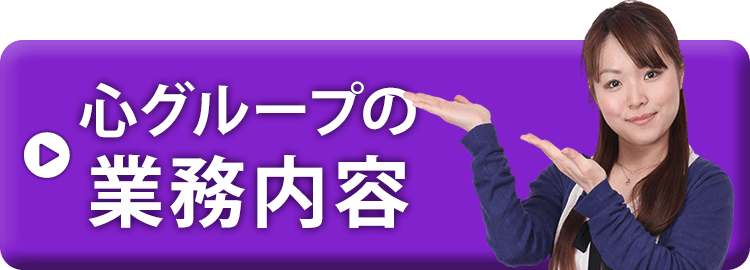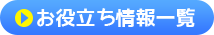相続手続きでは何をしなければならないか
1 相続手続きにおいて重要なもの
相続の際には様々な手続き等が必要になりますが、特に重要なものは、「遺産総額の把握」「相続人の確定」「遺言の有無の確認」「遺産分割協議」「相続税の申告」です。
それぞれについて、いつ・どのように行えばよいのか、各種の相続手続きを進める上での注意点を知っておくことがとても重要です。
2 遺産総額の把握
⑴ 遺産総額を把握する必要性
遺産総額の把握は、相続手続きの中で初めに取り掛かる必要があります。
被相続人の遺産のうち、プラスの財産よりも借金のようなマイナスの財産が多い場合は、相続をすると返済の義務まで相続することになってしまいます。
このような場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、プラスの財産も放棄することになりますが、マイナスの財産も相続しなくても済みます。
ところが、この相続放棄の手続きには期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時、つまり自分が相続人になったことを知った時から原則として3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述を行わなければなりません。
申述を行う家庭裁判所は、例えば、被相続人の最後の住所地が名古屋市内であった場合は、名古屋家庭裁判所となります。
遺産の全体像が把握できなければ、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断できませんので、遺産の全体像の把握を最初に行う必要があるのです。
⑵ 不動産
被相続人が不動産を所有していた場合は、毎年、被相続人の住所地に固定資産税納税通知書が送られている可能性が高いため、それを探せば、どこにどのような不動産を所有しているかを確認することができます。
もっとも、課税標準額が免税点(土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円)未満である場合は、固定資産税が課税されず、納税通知書が送られなかったり、送られるとしても納税通知書に財産が記載されていなかったりします(公衆用道路等は記載されないことがあります)ので、この方法は確実ではありません。
もし、名古屋市内に不動産を所有していると聞いているものの、具体的にどこにあるかは分からないという場合は、名古屋市役所で固定資産評価証明書を発行してもらい、所在と評価額を調査するのが確実だといえます。
参考リンク:名古屋市・評価証明・物件証明の申請
⑶ 預貯金
自宅などに通帳があれば、記帳することで預貯金の額を知ることができます。
もし通帳が無くても、被相続人が生前利用していた銀行などが分かるのであれば、取引明細書や残高証明書を発行してもらうことで、預貯金の額を把握することができます。
被相続人がどこの銀行を利用していたか全く分からない場合は、全国の金融機関を網羅して調査できるような手続きはないため、勤め先の給与振込みがされていた銀行を調べるなど、被相続人が利用していそうな口座について、手当たり次第調査する等の方法を用いることとなります。
弁護士に相続の案件を依頼されている場合は、弁護士会を通してそれぞれの金融機関の本店へ照会を行えるため、口座が存在する支店を確認できることも多いです。
⑷ 株式・公社債・投資信託などの金融商品
株式などを保有していた場合、窓口となっている証券会社や銀行から、特定口座年間取引報告書が送られるので、それが見つかればどこに株式などを保有しているのかを調べることができます。
窓口となっている証券会社や銀行が分からない場合は、証券保管振替機構に名寄せを依頼することにより、窓口の特定ができることもあります。
⑸ 借金
金融機関から請求書や督促状が届けば、被相続人がどこで借金をしているのかが分かります。
もっとも、すぐには請求書や督促状が届かないこともありますので、念のため、信用情報機関への問合せを行うことをおすすめします。
問合せ先の信用情報機関は、借入れをしていた金融機関ごとに異なっており、銀行の場合は全国銀行個人信用情報センター、クレジット会社の場合はCIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)、消費者金融の場合はJICC(日本情報信用機構)が問合せ先となっています。
3 相続人の確定
相続人は自分たちだけだと思っていたのに、養子縁組などにより、後になってから他にも相続人がいることが判明したというケースは、時々見受けられます。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないとされているため、そのような場合には、一部の相続人だけで行っていたとしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
ですから、遺産分割協議を行う場合には、前もって、戸籍を調査し、相続人が誰であるのかを確定させなければなりません。
そのためには、市区町村の戸籍課で、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、全部事項証明を交付してもらい、それらの記載内容を確認する必要があります。
結婚等により転籍している場合は、転籍前の戸籍もさらに必要となります。
このようにして、被相続人の出生までさかのぼって、戸籍を取得することが必要となります。
ちなみに、被相続人の本籍がどこか分からないという場合は、被相続人の死亡時に住民票があった市区町村へ住民票の交付を請求すれば、住民票に記載された本籍地を確認することができます。
除籍謄本については、保管期間が経過すると廃棄してしまう自治体もありますが、そのような場合には、廃棄済証明書を発行してもらうことができます。
4 遺言の有無を確認
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言の内容に従って遺産分けがなされることとなりますので、遺言の有無は非常に重要です。
遺言には、被相続人が自筆で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成してもらう公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、相続人であれば、全国どこの公証役場でも、被相続人の遺言が無いかを検索することができます。
5 遺産分割協議
被相続人の遺言が無かった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決めることとなります。
民法では法定相続分を定められていますが、相続人の合意によってその割合を変更することもできますし、相続人のうちの誰かがすべてを取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払うということも可能です。
6 相続税の申告
相続財産の課税価額が基礎控除額に収まる場合は、相続税の申告を行う必要はありませんが、そうでない場合は相続税の申告を行わなければなりません。
申告には期限があり、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続手続きで注意すべき期限 法定相続情報一覧図を作成するメリット
相続が発生した場合に必要な手続き
1 相続発生後は必要な手続きがたくさんある

相続が発生した場合、死亡届・火葬許可申請書の提出、年金手続、健康保険の諸手続、世帯主変更手続、公共料金の支払方法の変更・停止、葬祭費・埋葬料の支給申請、相続するかあるいは相続放棄か限定承認をするかの選択、準確定申告、相続税申告、遺言書の検認、遺産分割、遺留分侵害額請求等、行うことが多々あります。
このうち、死亡届・火葬許可申請書の提出、健康保険の諸手続、相続放棄や限定承認、準確定申告、相続税申告、遺留分侵害額請求等には、期限があります。
期限が存在する手続きの中には、期限を過ぎてしまうと、相続放棄や限定承認ができなかったり、延滞税や無申告加算税等のペナルティを課せられたりと、取り返しのつかないことになる場合もありますので、注意が必要です。
以下では、相続における代表的な手続きについて、ご紹介いたします。
2 死亡届・火葬許可申請書の提出
相続が発生した後、7日以内に、死亡届・火葬許可申請書を提出する必要があります。
実際の手続きとして、死亡届・火葬許可申請書については、被相続人(亡くなった方)が亡くなった場所や本籍地、届出をする方の所在地のいずれかの市区町村役場に書類を提出する方法で行います。
死亡届・火葬許可申請書の書式は、市区町村役場の窓口で取得することができます。
必要な書類は、死亡診断書または死体検案書、印鑑です。
火葬許可申請時に、所定の火葬料を支払う場合があるため、詳細は、市区町村役場で確認する必要があります。
なお、死亡届・火葬許可申請書の手続きについては、葬儀を葬儀会社に依頼した場合、一般的には、葬儀会社が代わりに行ってくれることがほとんどですので、ご遺族の方が行うことはほとんどありません。
3 年金の手続き
年金を受給している方が亡くなった場合、亡くなった方の住民票の住所地を管轄する社会保険事務所で受給停止などの手続きを行う必要があります。
厚生年金を受給していた場合、亡くなってから10日以内に手続きを行う必要があります。
他方、国民年金を受給していた場合は、亡くなってから14日以内に手続きを行う必要があります。
年金関係の手続きを行うためには、年金証書、死亡診断書、戸籍などが必要です。
年金手帳が見つからない場合は、紛失届などの提出が必要になる場合があります。
4 健康保険証の手続き
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、保険は必要なくなるため、その手続きを行う必要があります。
具体的には、国民健康保険資格喪失届を、亡くなった方の住民票上の住所の市区町村役場に提出します。
この届出は、亡くなってから14日以内に行う必要があります。
国民健康保険資格喪失届を提出するときは、健康保険証を返還しなければいけません。
また、手続きを行う際は、国民健康保険の保険証や、運転免許証などの本人確認書類などが必要です。
5 介護保険の手続き
亡くなった方が、介護保険の被保険者だった場合、介護保険に関する手続きが必要です。
具体的には、介護保険の資格喪失届を市区町村役場に提出します。
また、亡くなった方が、要介護認定を受けていた場合、介護被保険者証を返還する必要があります。
手続きを行う場所は、亡くなった方の住民票上の住所の市区町村役場です。
6 世帯主の変更手続き
世帯主が亡くなった場合、世帯主の変更の手続きを行わなければいけない場合があります。
もっとも、残された世帯員が1人だけの場合は、世帯主変更の届出をする必要はありません。
また、残された世帯員が15歳未満の子と、親権者の2人だけの場合も、世帯主変更の届出は必要ありません。
7 住民票の抹消手続き
亡くなった方の住民票を抹消する手続きが必要です。
もっとも、死亡届を提出すれば、自動的に役所が手続きを行いますので、特に提出する書類はありません。
8 相続放棄・限定承認
被相続人に多額の借金がある場合、もしくは、借金があるかもしれない場合、相続を放棄すること(相続放棄)や、借金の範囲で遺産を取得すること(限定承認)があります。
この相続放棄・限定承認の手続きには、3か月の期間制限があり、この期間を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄・限定承認ができなくなり、自動的に相続したことになります。
特に被相続人に借金がなければ問題となることは少ないですが、多額の借金があった場合、取り返しのつかないことになる場合がありますので、注意が必要です。
相続放棄・限定承認は、3か月の期限内に、必要書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する方法で行います。
9 準確定申告
被相続人が個人事業や不動産賃貸を行っていた場合や、多額の医療費を貰っていた場合は、4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
準確定申告とは、簡単にいうと、相続人等が被相続人の代わりに被相続人が行う予定であった所得税の確定申告をすることです。
期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられるため、注意が必要です。
実際の方法としては、確定申告書と申請する人の本人確認書類、収入や支出に関する客観的資料を添付して、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納税します。
10 相続税申告
被相続人の財産が一定額を超える場合、10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
この一定額については、基礎控除額といい、相続財産の価額が「3000万円+法定相続人の数×600万円」以上の場合は、相続税申告が必要になります。
相続税申告については、相続税申告書と遺産に関する書類等を被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する方法で行います。
相続税申告については、税理士に頼んだ場合でも、どの税理士に依頼するかによって、相続税額が変わると言われるほど、専門性が高いため、相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
11 遺留分侵害額請求
遺言書が存在し、その内容が特定の相続人等に全財産を相続させるといった内容であった場合や、被相続人から相続人等に多額の生前贈与があった場合、遺産を多く受け取った相続人等に対し、1年以内に遺留分侵害額請求をしないと、遺留分侵害額請求が認められなくなることがあります。
そもそも、遺留分とは、簡単にいうと、相続人に認められた最低限度の相続の権利のことをいい、被相続人から見て、兄弟姉妹、甥姪以外の相続人に認められています。
そのため、特定の相続人には財産を渡さないという遺言書があったとしても、その相続人は、遺留分として、一定額のお金を請求する権利があります。
遺留分侵害額請求の具体的な方法は、一般的に、遺言書で多く財産を貰う相続人等や多額の生前贈与を受け取った相続人等に対して、「遺留分侵害額請求を行う」という内容の内容証明郵便を送ることが多いです。
遺留分侵害額請求を行った後、遺産等を多くもらった相続人等と協議し、協議がまとまらない場合は、調停や訴訟といった裁判手続きを行うことになります。